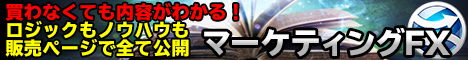保育新制度子どもを守る自治体の責任 [ 中山徹 ]
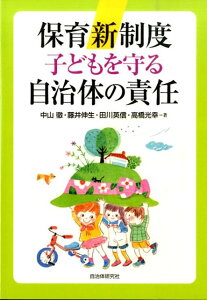
中山徹 藤井伸生 自治体研究社ホイク シンセイド コドモ オ マモル ジチタイ ノ セキニン ナカヤマトオル フジイノブオ 発行年月:2014年08月 ページ数:88p サイズ:単行本 ISBN:9784880376196 第1章 新制度の本質とこれからの展望(新制度、2つの本質/待機児童解消は小規模保育事業に依存 ほか)/第2章 新制度の自治体での具体化、対応のポイント(施設・事業の認可基準等/確認制度に関する運営基準 ほか)/第3章 新制度と自治体の責任、保育実施義務(新制度での保育所利用・保育必要量の認定手続き/児童福祉法第24条の留意点保育の実施義務 ほか)/第4章 認定こども園、幼保一体化の課題(公定価格で誘導!?/認定こども園では「教育」が受けられる!? ほか)/第5章 保育の現場で豊かな保育を守る(公立保育所の中に広がる不安/公立保育所における現場の運動と実践の課題) 本 人文・思想・社会 教育・福祉 福祉
価格:1,000円
自治体の平和力 “まち”がその気になれば、戦争だって、とめられる。 (岩波ブックレット) [ 池尾靖志 ]

“まち”がその気になれば、戦争だって、とめられる。 岩波ブックレット 池尾靖志 岩波書店ジチタイ ノ ヘイワリョク イケオヤスシ 発行年月:2012年08月 ページ数:62p サイズ:全集・双書 ISBN:9784002708485 池尾靖志(イケオヤスシ) 1968年、名古屋市生まれ。立命館大学社会システム研究所客員研究員。平和学、国際関係論専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 1 自治と平和の深い関係/2 「国策」に抵抗する自治体/3 平和政策は政府の「専管事項」か/4 自治体が平和のためにできること/5 沖縄に見る民衆と自治体のパワー/6 自治体の平和政策の限界/7 自治体の平和政策が世界を変える 自分たちのことは、自分たちで決める。これを「自治」という。私たちは、自分たちの暮らす地域の自治を確立していくことによって、自分たちの力で平和を築くことができる。平和と安全保障の問題は、私たち自身と地域の問題でもある。平和展や姉妹都市交流といった自治体の事業の意味を問い直し、非核自治体宣言、非核港湾条例といった、地域から平和をつくりだしていく自治体の動きを紹介する。 本 人文・思想・社会 政治
価格:540円
ケーススタディ行政不服審査法 自治体における審査請求実務の手引き[本/雑誌] / 中村健人/著 荻野泰三/著 山下将志/著
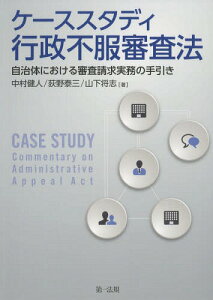
★書籍商品の購入に関するご注意コチラ↓より、初回盤・特典の詳細、在庫情報・出荷状況をご確認ください。<内容><商品詳細>商品番号:NEOBK-2204922メディア:本/雑誌発売日:2018/03JAN:9784474063396ケーススタディ行政不服審査法 自治体における審査請求実務の手引き[本/雑誌] / 中村健人/著 荻野泰三/著 山下将志/著2018/03発売
価格:3,024円
議会と自治体 2018年 08月号 [雑誌]

日本共産党中央委員会出版局ギカイトジチタイ 発売日:2018年07月24日 予約締切日:2018年07月20日 B5 03205 JAN:4910032050880 雑誌 ビジネス・投資 社会・時局
価格:779円
【送料無料】 都道府県出先機関の実証研究 自治体間連携と都道府県機能の分析 / 水谷利亮 【本】

基本情報ジャンル社会・政治フォーマット本出版社法律文化社発売日2018年05月ISBN9784589039286発売国日本サイズ・ページ228p 21cm(A5)関連キーワード 9784589039286 【FS_708-2】出荷目安の詳細はこちら>>楽天市場内検索 『在庫あり』表記について
価格:5,616円
自治体の議会事務局職員になったら読む本/香川純一/野村憲一【1000円以上送料無料】
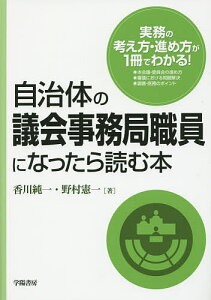
著者香川純一(著) 野村憲一(著)出版社学陽書房発行年月2015年04月ISBN9784313180475ページ数230P9784313180475内容紹介実務の考え方・進め方が1冊でわかる!本会議・委員会の進め方、審議における問題解決、調査・庶務のポイント。※本データはこの商品が発売された時点の情報です。
価格:2,700円
自治体大好き人間大集合~♪
「ボランティアには行けないから寄付をしたい。」
「どこに寄付をしたらいいか分からない。」
そろそろ、こうしたご寄付に関するお問い合わせを多くいただくようになってきました。まずは、災害時の寄付の使われ方をご紹介します。
お見舞金などとして被災された方々に直接渡され、それぞれの生活再建のために活用してもらうためのお金が「義援金」。一方で、避難所や在宅避難されている方々のために物資配布や医療支援などの支援活動を行うNPO等の活動費として使うためのお金が「支援金」です。
このように、「義援金」と「支援金」では、第一に届く相手が違います。「義援金」は、日本赤十字社や市町村などを通じて直接被災された方々に届き、「支援金」は支援活動を行うNPO等に届きます。「支援金」は、寄付をするあなたが応援したい、関心のある分野のNPO等を選んで寄付をすることができるということでもあります。
第二に、「義援金」と「支援金」は、被災地に届くタイミングが違います。「支援金」は受領したNPO等が行う人命救助や避難所支援などにすぐに活用される一方、「義援金」は被災者数を正確に把握したうえで均等に分配されます。それらの把握や配布作業を行うのは被災自治体ですから、大きな災害であるほど、配布されるまでに時間がかかります。
のホームページに分かりやすい図がありますのでご参考までにご紹介します。
今回の豪雨災害について、実際の寄付先をいくつかあげます。どこに寄付するかは、下記のURLなどを参考にしていただき、最終的にはご自身でご判断してください。
<義援金>
日本赤十字社
中央共同募金会
※支援金も集めています。
<支援金>
(特活)全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)
災害発生後、支援の必要なところへ効果的に支援を届けるコーディネーション(調整)を担う全国組織。広島県及び岡山県を中心に、行政、社会福祉協議会、NPO等の連携に取り組んでいる。
(特活)ジャパン・プラットフォーム
紛争や災害時の緊急・人道支援を行う国際NGO。東日本大震災、熊本地震で国内の災害支援を展開。ほとんどの災害支援系の国際NGOが加盟しており、広島県、岡山県、愛媛県で調査を実施、地元ニーズに合った被災者支援活動を実施中。
災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(支援P)
中央共同募金会が設置主体の、NPOや社会福祉協議会等による共同体。災害ボランティアセンター設置支援などを行っている。
(特活)レスキューストックヤード
愛知県名古屋市を拠点に、阪神淡路大震災以降35か所以上で災害支援に携わるNPO。岡山県倉敷市、岐阜県で避難所支援を中心に活動中。
ももたろう基金(みんなでつくる財団おかやま)
岡山県のコミュニティ財団である(公財)みんなでつくる財団おかやまが設立した基金。この基金から、主に岡山県内の地元NPO等が行う支援活動に助成される。
西日本豪雨災害支援基金(コミュニティ未来創造基金ひろしま)
広島県のコミュニティ財団である(公財)コミュニティ未来創造基金ひろしまが設立した基金。この基金から、主に広島県内の地元NPO等が行う支援活動に助成される。
(一社)ピースボート災害ボランティアセンター
主にボランティア派遣による災害支援を行うNPO。岡山県倉敷市真備町において避難所運営や生活支援の活動を実施中。
以上、ご紹介した団体のほかにも、豪雨災害で被災者支援活動を実施中の多くのすばらしいNPO/NGO等がございます。
被災地には長期間の支援が必要です。ご寄付を検討される場合には、一度に高額ではなく、複数回に分けて行う方法もあります。いずれにせよ、団体ホームページ等で、団体の基本情報やこれまでの活動実績などを確認のうえ、ご自身の判断で寄付先を選んでください。
自治体は堂々通販ランキング入賞、各商品の特徴やリスク、使い勝手をプロのコメントとあわせて紹介します。









〜0:59の6時間限定タイムセールでお安くなるみたいです!




自治体人気のコレクション
2時間待ちなんだって。
何それって思うけど改善してないみたい
おかしいでしょ。
これは市長とか、知事が能力が無いんだと思う。
那覇市だけの問題じゃないので、県の問題なんだろうね。
韓国客誘致が大事なのに、こういうことを改善をしない。
おかしい・・・・というか、やっぱり何か間違ってる気がします。。
ーーーーーーーーーーーーーー
沖縄「レンタカー長時間待ち」どう解決するか
2018年8月17日 8時0分
公共交通の利用促進に向け、今回データが整備される公共交通機関はモノレールとバス、そして離島をつなぐ航路だ
沖縄本島がいま、レンタカー利用拡大の対応に追われている。
沖縄県内のレンタカー台数は2012年3月から2017年3月の5年間で約1万台増えた。
そのうちの8割は沖縄本島で営業を行う車両で、約7000台増えている。
沖縄の玄関口となる那覇空港の送迎場では、多くの人がレンタカー会社の送迎車を待っている光景が見られる。
いま、沖縄県はこの「レンタカー送迎車待ち」問題解消に取り組んでいる。
そこで白羽の矢が立ったのが「公共交通の利用促進」だ。
沖縄での取り組みに迫った。
レンタカーを借りるまでに2時間
7月のある平日。昼頃の那覇空港へ行くと、通称「中の島」と呼ばれる送迎場では多くの利用客が各レンタカー会社の送迎車を待っていた。
送迎車も続々とやってきてはお客を乗せるが、待っている客は増える一方で、送迎が追いついていない。
沖縄県が行った2016年の調査では最も混み合う11時30分~13時に最大約470人がここで送迎を待っていたという。
この混雑が原因でレンタカーを借りるまでに2時間かかることもあり、初めての観光客は空港ですぐレンタカーが借りられると思ってくる人も多いことから、満足度の低下が心配されている。
また、問題は空港だけにとどまらない。
本島内のホテルなど、観光産業の「受け入れ側」でもレンタカー増加による駐車場不足に頭を悩ませる。
駐車場拡張を余儀なくされたり、施設から離れたほかの駐車場へ案内したりする必要が生じており、それも課題となっているようだ。
送迎待ちの問題は観光が主力産業となる沖縄では関心も高く、2016年頃から県内のメディアで取り上げられ、県議会でも話題となった。
そこで2016年度から、沖縄県はこのレンタカー会社の送迎待ちの解消に取り組むようになった。
那覇空港でのレンタカー営業所への送迎待ちの様子
まず2016年度は実態調査を行うことで原因と課題を洗い出し、2017年度にはレンタカーの混雑予報の提供、レンタカーを借りる場所の分散化、リムジンバスを用いたレンタカー送迎客の輸送の実証実験といった取り組みを行った。
この取り組みにより、中の島の待機人数は約470人から約300人まで減った。
また、OTSレンタカーでは自社運行と路線バス会社との契約費を比較検討し、今年4月から送迎車を路線バスに切り替え、レンタカー利用者はバス運賃無料という取り組みをはじめた。
観光客に使いづらいバス
だが、このままレンタカーの営業台数が増え続ければ、いずれ限界がくる。
「短期的にはインフラ改善で効果はあるかもしれないが、このままレンタカーが増えてしまえば価格競争に陥り、いずれインフラ的にもレンタカー業界的にも限界がきてしまう。
そこで、そもそもレンタカーをなぜ使うのかという根本的なところから考えた」。
こう語るのは沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課観光資源班長の大仲浩二氏だ。
>
沖縄県庁近くの「パレットくもじ」前の朝の様子。
県内各地から発着する多くのバスが行き交う
そこで県は観光客の声を集めた。
すると、那覇空港の案内所における観光客の問い合わせのおよそ8割は交通機関に関する内容ということがわかった。
路線バス関係の問い合わせが最も多く、国内線ターミナルの案内所では全体の4割が路線バスに関する問い合わせだったというから驚きだ。
なかでも「観光地へ行ける路線バスがないのか」という問い合わせや「バスの乗り方がわからない」という声が多かったという。
この声を受け、沖縄県では実際に路線バスの情報が調べられるのかGoogleマップで検索し、検証を行った。
すると、モノレール(ゆいレール)と空港発着のわずかなバス系統の情報は検索できたが、ほとんどの路線バスの情報はGoogleマップで調べられないことがわかった。
たとえば、有名観光地であるひめゆりの塔や斎場御嶽(せーふぁうたき)へは、実際は1日10往復以上あるバスでアクセスできる。
しかし、Googl
eマップ上には路線バスが表示されず、バスでは行けない場所として扱われていたのである。
さらには座間味島をはじめとした離島航路も調べられなかったという。
一方で、国内のほかの観光地では離島航路やバスがきちんと検索可能なところもあるとわかってきた。
そこで今年度から2カ年でバス情報、モノレール情報、航路情報、レンタカー情報、観光地情報などを網羅的に整備し、オープンデータとして公開しようという計画が始まった。
バスやモノレール、航路の情報はGTFS形式で整備し、Googleマップに反映させることで、経路検索で路線バスなどの交通機関が漏れなく表示されるようにする。
そして観光客に公共交通機関の存在を「認知」し、利用してもらおうというのだ。
経路検索サービスはほかにもある。
その中でもGoogleマップへの交通情報の掲載に沖縄県がこだわるのは、沖縄県にやってくる外国人観光客の増加にある。
彼らは日本国内で開発された経路検索サービスの多くは使えず、世界共通の「Google」を頼るのがほとんどだからだ。
外国人も地元住民も使える案内を
昨年度の統計では沖縄県の年間観光客数約958万人のうち約269万人が外国からの観光客だった。
外国人観光客数の伸び率も前年比約26%増と、いま伸びに伸びている。
内訳では台湾が年間約81万人と最も多く、続いて年間約54万人で韓国と中国が並ぶ。
国際免許に関するジュネーブ条約に参加している韓国・台湾からの観光客は、レンタカーの利用が少なくないという。
沖縄県内ではバスが公共交通の主力だ
しかし、日本人が海外に行くときにレンタカーを積極的に借りるだろうか。
どうしても現地に行く交通手段がないか、不確実な場合に仕方なく借りることが多いのではないだろうか。
これは日本に来る外国人観光客も同じだ。
また、最近ではGoogleマップ片手の外国人に店の場所や交通機関の乗り方を聞かれることは珍しくない。
「(ある場所への)行き方を聞かれたとき、使ったことのある見慣れた地図であれば地元の人も案内がしやすい。
そして、地元の人の案内で外国人観光客をサポートできればおもてなしにもなるし、観光客の満足度向上につながる」と大仲氏は言う。
そのためには地元の人も同じような地図を、ひいては公共交通を普段から使っていることが重要だ。
そこで国内観光客、外国人観光客、そして地元住民が皆使えるGoogleマップで検索しやすくすることが重要になってくるのだ。
夕方、混雑する那覇市内の道路を走るバス
一方で、沖縄本島を走る路線バスは地元の人によく使われているかというと、決してそんなことはないのも現状だ。
路線バスの旅客輸送分担率は5%未満で、県民一人が1年間でバスを利用する回数は平均19回(2014年調べ)。
その一方で自家用車主体の交通となっている那覇市街は交通渋滞に悩む。
混雑時の平均速度は15.9km/h(2014年度)で、三大都市圏よりも混み合っている。
そのため、地域ICカード「OKICA」導入や国道58号に10.4km(南行き・朝時間帯規制)のバス専用レーンを設けるなどの施策で路線バスの利用促進をしようとしているが、まだまだ道半ばだ。
そこで観光客の移動支援と県民向けの公共交通利用促進を同時に行おうというのが、今回のバスやモノレール、航路、レンタカーの情報整備というわけだ。
「賢く公共交通もレンタカーも利用してほしい」と大仲氏は語る。
観光業者とバス会社には温度差
もちろん、この事業には課題もある。
1つは観光事業者とバス事業者の温度差、もう1つは持続的なデータ整備の組織作りだ。
7月に行われたデータ整備へ向けた委員会では、観光事業者側から
「バス会社は前のめりになってほしい。これまでは県民140万人を相手にした商売だったかもしれないが、観光客を入れれば一気に市場は1000万人に広がる」
「バス旅はいま観光のトレンドになりつつある、広めていきたい」
という積極的な意見が出た一方で、交通事業者側からは
「一部の路線だけ恩恵を受けて終わりとならないか心配だ」
「バス事業者にはGTFS形式のデータというのがよくわからない」
と及び腰になっている部分も見られた。
沖縄に限らず、一体的なデータ整備の取り組みには、交通事業者側の不安がぬぐいきれずにデータ整備の大きなハードルとなるケースが多い。
本来はこうしたオープンデータは事業者の生産性向上に役立つものだ(東洋経済オンライン5月20日付記事「『グーグルマップ』に載るとバスは便利になる」)。
しかし、データ整備による具体的な恩恵が見えにくいことや、情報を提供することで想定されるクレームに対する不安がどうしても事業者に二の足を踏ませる。
一方で、早くも自主的にGTFS形式のデータを整備した事業者も出てきた。
那覇空港と美ら海水族館や本島北部の運天港を結ぶ「やんばる急行バス」ではGTFS形式のバス情報整備を行っており、那覇空港では実際にGoogleマップで調べ、やんばる急行バスを使う観光客も出始めているという。
継続的にデータ整備・更新を行ってくれる事業者選定も課題だ。
補助事業としてデータ整備が行われるのは2カ年。
しかし、その後もデータ更新を続けていくことが、継続的に公共交通を使ってもらうためにも、最新の観光情報を提供するためにも重要になる。
委員会では、今回公募する事業者には継続的なデータ更新に関するポリシーを聞くことや公募事業者が自主事業として続けていくための財源確保についてさまざまな提案がされたが、決定的な案は出なかっ
た。
補助事業終了後のデータ更新は、今後大きな課題となっていくだろう。
観光と交通の悩みは解決できるか
ここまで沖縄本島のレンタカー送迎待ち対策から観光における公共交通利用促進につなげる取り組みを見てきた。
ポイントは、交通業界だけの動きにとどまらず、観光業界をつなげ双方の悩みを一石二鳥で解決しようという考え方だ。
一般的に交通事業は、どうしても事業に補助金などがつきにくく、プレイヤーのやる気を喚起しにくい傾向にある。
一方、観光業界は収益が上がっている一方で、観光客の移動手段であるレンタカー受け入れに困っている。
この2者をつなげることで議論を活性化し、複数の課題を同時に解決していこうという考え方は、まさに観光が大きな産業である沖縄らしい取り組みといえよう。
また、データの利活用や事業の効果測定に関しても、観光という「目的地」側が参加していることでやりやすくなる。
たとえば、ホテル側でアンケートを行うことで、かなり有用なデータが収集できる可能性がある。
また、整備した頃にハッカソンやアイデアソンを行い、コンテストを行えば、インバウンド増加で盛り上がる観光関係のアプリを開発したい国内の開発者はもちろん、地理的に近い台湾の開発者が多く参加してくることも期待できる。
こうした動きがうまく出てくれば交通事業者は自然に参加していくことだろう。
ただ、繰り返しにはなるが、継続的なデータ更新のための仕組み作りがやはり大きな課題だと感じられる。
これについては、観光系のNPO組織が引き受け、観光事業者やレンタカー事業者から寄付金として資金を調達する仕組みも考えられる。
自治体がデータ整備を引き受けてしまうと、データ整備や更新が単純な「コスト」となり、また民間の力による有効活用もされにくくなってしまう。
そうすると事業としての有用性が疑われ、せっかくのデータ整備も尻すぼみとなってしまう可能性がある。
それを避けるためにも民間の力を活かし、補助金に頼らない自然な資金調達体勢をうまく引き出すこともデータ整備・更新の鍵と言えるだろう。
筆者は取材の際、那覇空港の「中の島」がレンタカー事業者の送迎待ちで混雑する横で、名護方面に向かう路線バスが誰も乗せずに発車していくのを見た。
数年後には、このバスに多くの観光客が乗る光景が生まれているだろうか。
=============
「空港ですぐレンタカーが借りられると思ってくる人も多い」
はあ?何それ、国際空港でしょ?
タイの地方空港以下じゃないの。
空港を大きくする前に、やっておべき事じゃないの?
政府からサービスを受ける事には熱心だが、サービス提供は苦手なんですかね?
ニコニコして、物を売りつけるのが観光じゃないからね。
サービスに対する概念が、韓国人に似てるのかもしれないね。
「駐車場拡張を余儀なくされたり」
当たり前のことだけど、駐車場ビルは無いのかね?
地権者がうるさいのかな?
空港拡張って、そういうのも含めてでしょ。
辺野古の埋め立ての100倍以上も埋め立てて、海を殺して滑走路作ってるんだから。
辺野古を環境破壊っていってるんだから、その10倍以上の環境破壊をやってるわけだし。
ジュゴンの生息域も潰してるんでしょ?
それだけの事をやりながら、駐車場とか、レンタカーとかが整備されてない訳?
それって、普通におかしいでしょ。
「リムジンバスを用いたレンタカー送迎客の輸送」
は?レンタカーの事務所まで連れてくってのが、そもそもおかしい。
レンタカーの事務所を空港内に置�
��て、レンタカーの駐車場ビルでも作るでしょ。
送迎者からリムジンバスって、発想が全く変わってないんだが。
大丈夫か?
「路線バスの情報はGoogleマップで調べられない」
「マップ上には路線バスが表示されず」
「離島航路も調べられなかった」
なんだ、なーんにもやってなかったんだ。
おもてなしなんか何もないって事ね。
酷いねえ、頑張れ沖縄!
それでいて日本のビーチには5つも選ばれてるんだぜ。
どんだけ自然に甘えてたかってことですわ。
勿体なさ過ぎです。
「Googleマップ片手の外国人」
タイでレンタカー借りると判るけど、ナビはついてません。
日本でも英語のナビはないよね。
タイではそのかわり、GOOOGLEマップやGARMINをナビに使います。
んでレンタカー屋では、GARMINを貸して呉れたり、GOOGLEを見る為に携帯のホルダーを取り付けたりしてくれるですよ。
勿論、車のシガーソケットからの充電器も一緒に。
日本のレンタカーには、そういう外国人用ナビの貸し出しは無いですよね。
「賢く公共交通もレンタカーも利用してほしい」
交通混雑を、観光客が自分で解決しろと言ってますよね。
検討委員会も素人じゃなくて、専門家に金払って、将来図を描いてもらったほうが良いと思うよ。
沖縄県人なんだから、みんなで検討したら、纏まらないって。
がははー
翁長知事、パフフォーマンスばかりで、実務能力は無かったのか、スタッフがろくでもなかったんだろうか。
沖縄タイムスも琉球日報も、こういう点では無能だよね。
政府叩きは出来るけど、沖縄を自分達で磨く事が出来ないんだから。
レンタカーだけの問題じゃないんだよね。
沖縄県の交通をどうするのか
県が考えなきゃどうしようもない事です。
これ、政府や他県のせいにはできんのでね。
そこは沖縄県にはつらい所かも知れないが。
「うちなんちゅう」だけで頑張れ。
そういう未来が描けない県に、借金返済が40年もかかる鉄道なんて、絶対無理だわ。
それにしても、沖縄県以外の人間を、全て「やまとんちゅう」でくくってしまうのは余りに失礼だよね。
夫々の県民性は、相当違うんだから。
沖縄県民だけが特異じゃないですよ。
クリックしてね!
↓ ↓ ↓ ↓
頑張れ日本!●
日本人に生まれてよかった!

自治体 関連ツイート
各都道府県トラック協会・各自治体名の入った
「緊急救援物資輸送中」の横断幕のあるトラックは
極めて重要で緊急の物資を輸送しています。
みなさんのご理解をよろしくお願いいたします。 htt…